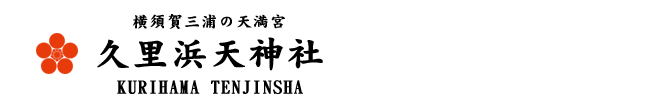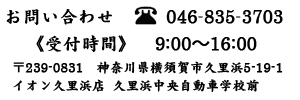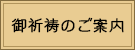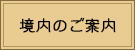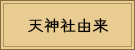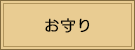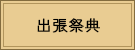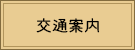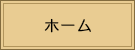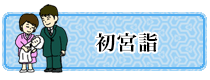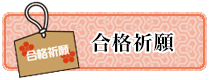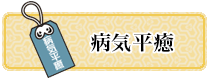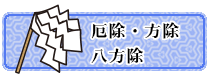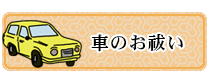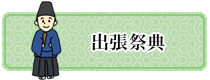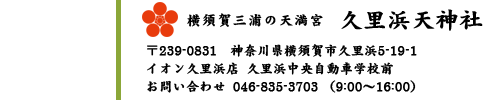ホーム > 天神様菅原道真公のお話 > その⑩讃岐に赴く【後篇】

第二十二話
その⑩讃岐に赴く【後篇】
道眞自身も「
情けない、さびしい、腹立たしい、こんな気持ちで一杯でした。菅原の家の今日を築き上げてくれた、祖父のこと父のことを考えれば、道眞の胸はつまるようです。
道眞は立ち上がって、家にまつってある孔子の廟の前を、何度となくゆきかえりしました。(こうし・・・中国、春秋時代の
少し下を向いて、足どりは重く、何を見つめているのやら、その眼には全く力がありません。その夜の道眞は、ほとんど眠れませんでした。
しかし、いよいよ讃岐へ出立する日の道眞の顔は、全く別人のように晴れ晴れとしていました。それは道眞の気持ちが、かわったからでした。道眞はその間に、こう気づきました。
「自分が学者として講義をするのも、或いは官吏として地方に赴くのも、どちらでも同じことだ。大君の限りなき御恩に報い奉るということに、どちらもかわりはない。ひとつ讃岐に行って、自分にあるだけの力を振るい、政治にはげんでみよう。そうだ、それが陛下への忠だ。日本人としての道は、それでつくされるのだ。」
見送りの人々が不思議に思うほど、道眞は心勇んで讃岐におもむきました。
始めての都を離れた生活であるだけに、さすがに都のかたが恋しく、そのさびしさを道眞は、詩に作って心を慰めていました。
しかし、讃岐国の政治には、非常に熱心でした。悪い病気がはやると聞けば、医者を連れて、家ごとに病人を見舞ってやりました。
仁和四年の夏は、あくる日も、あくる日も毎日の日でりで、川の水はかれてしまい、田の稲は今にも枯れそうでした。百姓達は困ってしまい、これでは今年は、お米がとれないと心配していました。道眞はこの様子を見て考えました。
「このように、ひでりがつづいて百姓が困るというのは、この国の政治にあたる自分に、徳がないからだ。百姓達にすまない。」
そう思うと、じっとしておられません。早速願文を作り、この国の
この間に道眞は一度休暇を賜って、京都に帰りました。讃岐の人々は、もはやふたたび讃岐国に来て下さらぬのではないかと、心配しました。そういって、心配する讃岐の人達に、道眞は、
「自分のいる別荘には、小松の種が蒔いてあるではないか。だから、きっとまた讃岐に帰って来る。」
という意味の詩を作って見せましたので、人々は、やっと安心しました。
道眞の讃岐に居たのは前後四年、
しかし、都にのこしたやしきは、あるじがいなくて荒れ果て、先祖代々集めたおびただしい書籍は、雨もりで汚れ、しみでいたむと思えば、讃岐に心は残りつつも、やはり都へと、その足は急ぐのでした。
時に道眞は46歳でありました。

ホーム > その⑩讃岐に赴く【後篇】